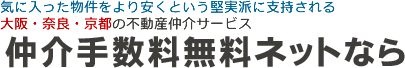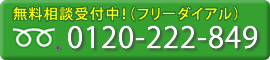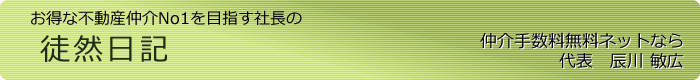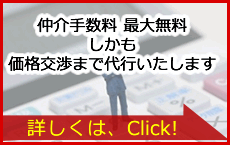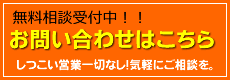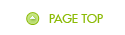こんにちは、辰川です。
フラット35の最大の特長といえば、何と言っても全期間固定金利ですね。
でも、民間金融機関である銀行にも、固定金利の住宅ローンがあります。
では、一体どんな違いがあるのでしょうか。
そこで今回は、銀行の超長期固定金利と フラット35の違いについて。
昨今、銀行の変動金利を使い、住宅ローンを組まれる方が多くなっています。
ところで、銀行ローンには、10年を超えるような超長期固定金利もあります。
では、フラット35と、銀行の長期固定金利とは、ともに固定金利。
そこには、どんな違いがあるのでしょう?
・まず、団体信用生命保険(略して団信)の有無があります。
「団体信用生命保険」とは、債務者が死亡または高度障害を負った際、
生命保険会社が残債務を弁済してくれるという制度。
フラットの場合、団信への加入は任意ですが、たとえ加入しない場合でも、
ふつう何らかの保険に加入する人がほとんどです。
一方、民間ローンでは、団体信用生命保険料を銀行が払うので、
保険料がかからないというメリットがあります。
・次に、保証料について
フラット35は保証料と繰上返済手数料がかかりません。
しかし、銀行の住宅ローンは保証料が原則必要。大体借入金額の2%、
つまり2千万円借りれば、40万円の保証料がかかります。
これは何故かと言うと、フラット35は、100%公的資金ではなくなったとはいえ、
住宅金融公庫が住宅ローンを証券化し機関投資家に転売するものなので、
万一のリスクは公庫と機関投資家が負担しているからです。
ところが、銀行の住宅ローンでは、銀行が全リスクを負うことになるので、
保証料が必要になってくるのです。
・審査基準について
ここでは、まず勤務年数や最低年収が問われます。
とはいうものの、フラット35では年収が基準に達しているかどうかは問いますが、
勤務年数や勤務先についてはあまり重要視しません。
一方、銀行は、年収の安定性を求めており、勤務年数や勤務先は重要視します。
つまり、フラット35の方が審査基準が低い=甘いといえます。
ですから、銀行の審査基準に乗らない人でも、フラット35であれば借りられる、
ということは知っておいて損はありません。
・フラット35を利用するには、購入対象の物件に一定の基準がある
つまり、フラットの「適合証明書」の発行を受けられるが絶対条件です。
これは新築でも中古住宅でも、物件自体が検査機関が行う検査に適合しなければ
融資が受けられません。これは気を付けたい点といえます。
いかがでしたか?
銀行の住宅ローンとフラット35には、金利以外の相違点も知っておく必要がありそうです。
どの住宅ローンが自分に合うのか迷ったときは、是非参考にしてくださいね。
次回は、フラット35の取り扱い金融機関について。
それではまた。