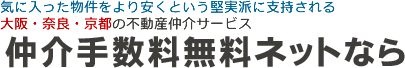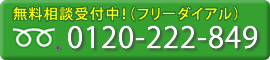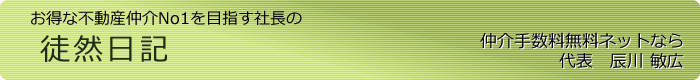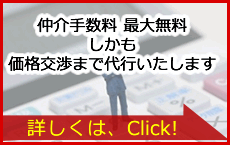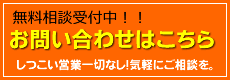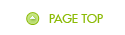こんにちは、辰川です。
マイホームを買って生活するには、
静かで落ち着いた環境も欲しいけれど、
近くにスーパーや飲食店があってほしいと
考えることもありますよね。
そこで今回は、住宅街と商業地が入り混じった
「第一種住居地域」と「第二種住居地域」について。
そもそも、用途地域とは何でしょうか?
大阪や奈良、京都などの市街地をみると、
一戸建てやマンションのほか、
スーパーなど商業施設、工場など
さまざまな建物があります。
どれも都市には必要なものですが、
例えば、住宅と工場が隣り合っていると、
住民から騒音や異臭の苦情があるものです。
その反対に、工場側ではこうした苦情を気にすると、
生産性の低下が起こる恐れも出てきます。
そこで、都市計画法という法律によって
「用途地域」を定めて、
そこに建てることのできる建築物の種類を
決めているのです。
ところで、用途地域の区分としては12種類あります。
例えば、一戸建てが目立つ「低層住居専用地域」と、
マンションが建築できる「中高層住居専用地域」があります。
そのほか、映画館や倉庫なども建てられる、
「近隣商業地域」や「商業地域」「準工業地域」「工業地域」。
工場のみに限定された「工業専用地域」があるのです。
こうした、用途地域のなかで、
とくに人口が密集したエリアが
「住居地域」といえます。
さて次回は、住居地域の特徴について。
それではまた。