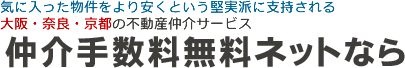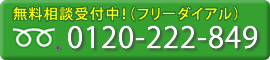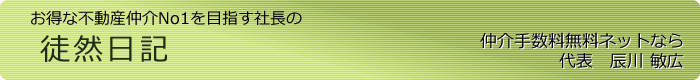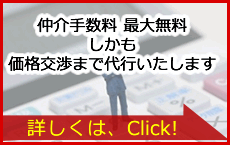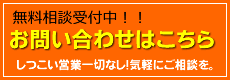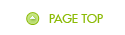こんにちは、辰川です。
今回は、一戸建ての火災保険の話をします。
建物が密集した市街地では、防火、防災のために燃えやすい建築をしめ出し、
耐火性能の高い建物を建てるように定めた地域があります。
これが、防火地域や準防火地域です。
大阪や奈良でも、購入したい物件のエリアが、防火地域や準防火地域にかかっていると、
必ず耐火構造にしなければなりません。
その逆で、防火地域や準防火地域以外で、わざわざ耐火仕様にする必要はありません。
ところで、火災保険会社では一戸建ての構造を3区分しており、
それぞれで火災保険料や地震保険料が異なります。
まず一般的な木造住宅は、H構造(非耐火構造)と呼ばれています。
次に燃えづらいのが、「省令準耐火」構造。これは、木造住宅が対象です。
さらに燃えづらいのが、準耐火建築物はT構造で、コンクリート造住宅や鉄骨造住宅が該当します。
この3つの区分によって、火災保険料が違ってきます。
そして、火災保険料を決める目安となるのが、T構造(耐火構造)とH構造(非耐火構造)。
ふつうの木造住宅(H構造)を「省令準耐火」仕様にすると、
火災保険と地震保険が約半額になります。これは、RC住宅と同じ保険料率です。
そもそも省令準耐火とは、ツーバイフォー住宅が日本に導入された頃に、
木造住宅と差別化するために、アメリカによる外圧で誕生したものです。
火災保険の保険料を決める目安が、T構造(耐火構造)とH構造(非耐火構造)なのですが
省令準耐火の木造は、T構造と同じで、火災保険と地震保険が約半額になります。
ですから、保険料を考えれば、せめて「省令準耐火」の木造にしたいところですね。
ところが、省令準耐火の認定を受けるには、規定の材料を使わなければならないので、
施工費が割高になってしまいます。
また見た目にも制約があって、柱や梁などの木部は室内から見えてはならず、
壁で覆い隠さないといけませんので、伝統的な日本家屋では認定は下りません。
ですから、保険料を安くするために、省令準耐火にしても大して意味はありません。
また万一、火事になって建物の半分以上が焼失しても満額が下りないので、
保険金だけで家を建て替えることはできません。
大阪や奈良、京都でも、建売り住宅のなかにはツーバイフォーで建てられて、
省令準耐火の認定を受けたものがあります。
この場合、省令準耐火にするかどうかは、事業者(売主)が決めることなので、
買い手のほうには選ぶことが出来ないという事情もあります。
このように考えると、木造を省令準耐火にするメリットとは、
火事がおきても家族が逃げられる時間をかせぎ、隣家からの類焼を防ぐという点にあるようです。
それではまた。