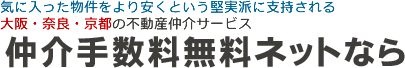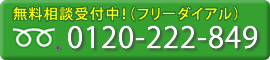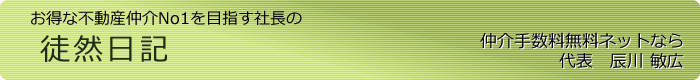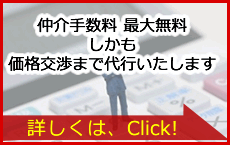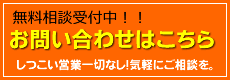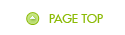こんにこにおこ近所にここんにちは、辰川です。
家の売却を効果的に行うには、いかに早く、多くの人に物件を知ってもらえるかが
ポイントといえます。そのために、チラシやネットの情報が最も近道です。
ところで、ご近所に知られずに家を売りたいと方も意外と多いです。
我が家の売却がご近所の関心事になってほしくない、売却理由を詮索されたくないという気持ちからではないでしょうか。
特にマンションの場合、ご近所に住む人にとっては販売価格そのものが自分の家の市場価格に影響する可能性もでてきます。
ところで、一番近所の人に知られる可能性が高いのは折り込みチラシです。
折り込みチラシは、家探しに全然興味のない人でも、たまたま目にするということが起こりえますね。
一方、ポスティングチラシは、エリアを限定することが可能。
「このエリア、このマンションを除いてチラシを入れてほしくない」と指定すれば、
近所の人に知られる可能性は低くなります。
ネット広告の場合は、検索をかけない限り、物件が販売されていることを知ることはまずありません。
従って、チラシは無理でも、ネット広告ならOKという売主様は多いです。
ところで、不動産の売却では、ご近所の人が買主になるケースは多いです。
なぜなら、子どもの学区を変えたくない、親のそばに住みたいといった理由で、エリアを限定して探す人は常にいるからです。
そのため近所の人を除外してしまうと、買主を見つける機会を狭める可能性があります。
当社の場合でいえば、通常3か月以内の成約を目指しますが、例えば2か月目で売却できる物件であれば、近所に知られずに販売にかけると1か月くらい余計にかかり、3か月目で売却できることが多いです。
もっとも、近所に知られずに売却する一番の方法は、不動産会社による買取です。
しかし、買取業者は若干リフォーム等を施したうえ、利益をのせて再販を掛けますから、
仲介を通じて売却するよりも明らかに売値は下がります。
近所に知られずに売却を望む場合は、仲介業者の相談しこんにちは、辰川です。
家の売却は、いかに早く、多くの人に物件を知ってもらえるかがポイントです。
そのためには、チラシやネットの情報が最も近道となります。
ところが、ご近所に知られずに家を売りたいという方もいます。
「我が家の売却が、ご近所の関心事になってほしくない」「売却の理由を詮索されたくない…」
その気持ちわからないではありませんね。
また、マンションの場合、ご近所に住む人にとっては、販売価格そのものが
自分の家の市場価格に影響する可能性もあります。
ところで、一番近所の人に知られる可能性が高いのは、折り込みチラシです。
折り込みチラシは、家探しに全然興味のない人でも、たまたま目にする
ということが起こりえる広告媒体といえるからです。
一方、ポスティングチラシは、エリアを限定することが可能。
例えば、「このエリア、このマンションを除いてチラシを入れてほしくない」と指定すれば、
近所の人に知られる可能性はうんと低くなります。
また、ネットに掲載する場合は、検索をかけない限り、まず販売自体を知ることはありません。
ですから、チラシは無理でも、ネット広告ならOKという売主様は多いのです。
ところで、不動産の売却では、ご近所の人が買主になるケースはとても多いといえます。
なぜなら、子どもの学区を変えたくない、親のそばに住みたいといった理由で、
エリア限定で家を探す人は常にいるからです。
そのため、近所の人を除外してしまうと、買主を見つける機会を狭める可能性があります。
当社の場合は、通常3か月以内の成約を目指しています。それが、例えば2か月目で売却できる物件ならば、
近所の人を除外すると1か月くらい余計にかかり、3か月目で売却できるケースが多いです。
もっとも、近所に知られずに売却する一番の方法とは、不動産会社による買取りですね。
ただし、買取り業者は、買い取った物件をリフォーム等を施し、さらに利益をのせて再販しますから、
仲介を通じて市場で売却するよりも、明らかに売値は下がってしまいます。
いかがでしたか?
ご近所に知られずに売却を望む場合は、まず仲介業者に相談してみることです。
チラシ、ネットでの告知をどのように制限するか、ぜひ相談に乗ってもらってくださいね。
それではまた。