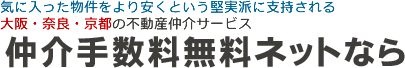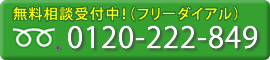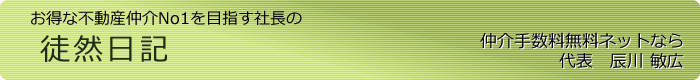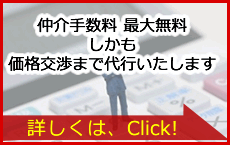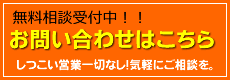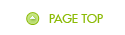こんにちは、辰川です。
前回は、民間の住宅ローンの場合、勤務年数や収入に関し、その銀行独自の基準がありますが、
フラット35では、申込人の勤務年数などは問われず、年収が低めの人でも借りやすいという話をしました。
さて今回は、民間の住宅ローンと、フラット35の金利について。
民間の住宅ローンの場合、おおまかに3つの金利の種類があります。
それぞれに変動型、当初固定金利型、全期間固定金利型といいます。
これに対して、フラット35は、全期間固定金利型のみ。
完済まで返済額がずっと変わらないという点で安心感はありますが、
現状では民間の変動金利のほうが利率が低いのは、実に悩ましいところ。
また、フラットを利用するには、建物に対する基準は厳しいために、
築年数の古い中古住宅では、その技術基準を満たせないことも多いです。
ところで、フラット35の中には、別に「フラット35S」という商品があります。
35Sとは、通常のフラットよりも耐震性や省エネルギー性に優れた住宅に対応した商品。
この性能基準を満たせば、5年間または10年間、0.6%金利が引き下げられるというものです。
そのほか、保証料については、民間の住宅ローンの場合、融資実行時に一括で支払う方法と、
金利に上乗せして支払う方法があります。
一方、フラット35では保証料は不要です。
さらに、団体信用生命保険(団信)にも、両者で違いがあります。
団信とは、住宅ローンの申込人が死亡または高度障害になった場合、残高分の保険金が
支払われて、住宅ローンが清算される保険。
この保険料が、民間の住宅ローンでは金利に含まれているため、とくに費用負担はありません。
ただし注意したいのは、民間の住宅ローンの団信では、申込人の健康状態によっては
加入できないケースも起こります。
つまり、健康状態に問題があれば、団信に入ることはできないため、住宅ローンを利用することは
できません。
一方、フラット35では、団信への加入は強制ではなく任意なので、現在、何らかの生命保険に
入っている人であれば、2重で保険料を支払う必要もなくなります。
いかがでしたか?
民間の住宅ローンと、フラット35では、単に金利の高低だけをみるのではなく、
自分の家計や働き方にマッチしているかも見てくださいね。
それではまた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆無料相談受付中!
大阪や奈良、京都で、一戸建てやマンションなどの不動産の購入・売却に
お悩みがある場合は、お気軽にご相談ください。