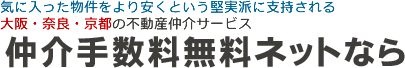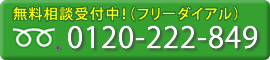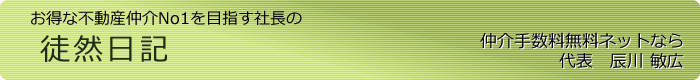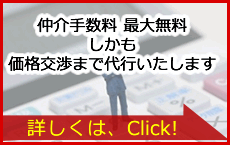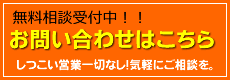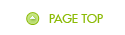こんにちは、辰川です。
不動産の広告には、マンションや一戸建ての間取りに、3LDKとか4LDKという表示があります。
そこで、○LDKの○の中に入る数字が大きいほど、広い家であることをイメージしがちです。
では、LDKの数字の大きさ=家の広さなのでしょうか?
2LDKとか3LDKといった表示は、間仕切り壁の多さを表しているだけで、
必ずしも家の広さを表すものではありません。
LDKとはリビング・ダイニング・キッチンの略であり、居間(リビング)と食事室(ダイニング)と
台所(キッチン)が一体となった部屋をいいます。
こうしたLDKの表記は、新築や比較的新しい中古住宅に多くて、
築30年くらいの中古住宅になると、4DKとか5DKのように、DKの表記が多いです。
また、最新のマンションには、「1LDK」であっても、
50??100?超の広さをもつ高級物件も存在します。
従って、LDKの数字が大きさ=家が広さ、ではないということですね。
ところで、不動産広告には、LDKと表示してもよい広さが大体決まっています。
例えば、LDK(リビングダイニングキッチン)は10帖以上のスペースがあり、
K(キッチン)は6帖未満、 DK(ダイニングキッチン)6帖以上10帖未満というように、
物件掲載基準が決まっています。
ちなみに、マンションなどには、2SLDKというように「S」の表示もありますよね。
このSとは、採光が規定以下しかない「サービスルーム」のことであり、例えば、
納戸など収納として使われる部屋を指します。
サービスルームには窓が無い場合と、小さめの窓が設けられている場合があります。
窓があれば、書斎や趣味の部屋として、利用することも可能ですね。
いかがでしたか?
同じ広さの家でも、2LDKもあれば3LDKもあるので、数字を大きさだけで判断しないことです。
不動産広告をみるときには、是非参考にしてくださいね。
それではまた。