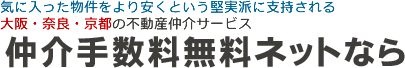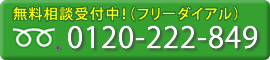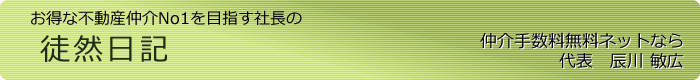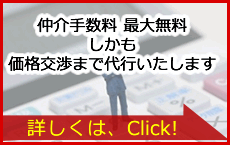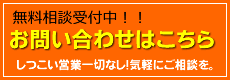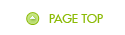こんにちは、辰川です。
前回は、都心の利便性を重視するならマンションになり、
居住性に重きを置くなら一戸建てになる、という話でした。
さて今回は、マンションと一戸建てを資産価値についてです。
まず、税法上の耐用年数からいうと、木造の一戸建てで22年、マンションは47年なので、
圧倒的にマンションの勝ちといえますね。
ただし、マンションは共同住宅という側面を忘れてはいけません。
つまり、一戸当たりの土地面積が僅かしかないマンションは、資産価値の大部分は建物のほうにあります。
そして建物の資産価値といえば、毎年確実に減っていき、最終的にゼロになります。
一方、一戸建ての場合、土地の資産価値は極端な値崩れが起きないので、ゼロにはなることはありません。
では、マンションは僅かな土地しかないから、数十年先には二束三文の資産価値しか残らないかといえば、
そんなことはなく、建物自体の耐久性は50年は十分にあります。
さらに、マンションが大規模修繕計画によって、資産価値が大きく損なわれない対処していますし、
特に人気エリアのマンションの場合では、資産価値の減少はなだらかになります。
一方、一戸建てのほうは、建物下落のスピードがマンションよりも激しいといえます。
ただし、これとて、一戸建ての所有者がきちんと修繕等のメンテナンスを行えば、
建物は40?50年程度は十分にもつものなのです。
結局のところ、資産価値という点では、マンションも一戸建ても、一長一短であり、
どちらかが一方的に有利と言い切れるものではありません。
はっきり言えることは、自分で建物をメンテナンスしていける人は一戸建てでも長らく維持できますし、
仮に建物が無くなったときでも、土地は資産として残ります。
その逆で、建物を自分でメンテするのは苦手で、むしろ管理組合や管理会社任せのほうが楽であるという人は、
一戸建てよりもマンションを選択したほうが、少なくとも自分が生きている間は、資産価値を維持できるといえるのです。
いかがでしたか?
マンションと一戸建て、どちらが資産価値があるかは、あなたの生活スタイルによっても変わってくるもの。
是非、あなたの住宅選びの参考にしてくださいね。
それではまた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆大阪や奈良、京都の新築、中古住宅、土地について無料相談実施中!
不動産の購入や売却でお悩みの方は気軽にお問い合わせください。
ご相談はこちら ⇒ web@bergehome.com