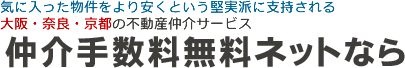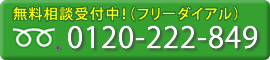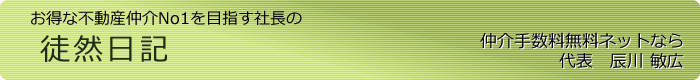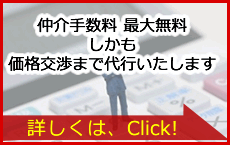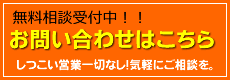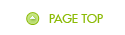こんにちは、辰川です。
やっと手に入れた待望のマイホーム。
でも、そんな新居に不具合が見つかったら、
これは悩んでしまいますよね。
このような不動産のキズや欠陥のことを、「瑕疵(かし)」といいます。
そして瑕疵について、売主が責任を負うことを「瑕疵担保責任」と呼んでいます。
ところで売買契約では、買主に対し、売主は自分が知り得る瑕疵を告知しなければなりません。
つまり、買主はそれを納得した上で不動産を購入することになります。
ただし、売主自身がそこに暮らしながらも、瑕疵に気付かないこともあり得ます。
これを「隠れたる瑕疵」といいます。
では、買主が引渡後に見つけた、隠れたる瑕疵について、
売主は責任を負うのでしょうか?
売主が不動産業者であれば、引渡後の一定期間、
売主が瑕疵担保責任を負うことになります。
なぜなら、不動産業者が売主であれば、当然、販売価格のなかに
利益が含まれていると考えられるからです。
その場合、売主業者は新築の場合で10年間、
中古物件なら2年間の瑕疵担保責任を負うことになります。
そして瑕疵の対象としては、雨漏り、構造体の腐食、
シロアリの発生、給排水の不具合などが挙げられます。
これに対し、中古住宅では当然、売主が個人のケースが多くなりますが、
個人が売主であれば、「売主は瑕疵担保責任を負わない」という特約も契約上、有効です。
ただ、売主がその欠陥を知っていながら、買主に告知しなかった場合には、
この特約は無効になるので、売主も注意が必要です。
また、たとえ売主である個人が、瑕疵担保責任を負う場合でも、
せいぜい2?3カ月間に短縮するケースがほとんど。
これは、個人の売主に瑕疵責任を過大に負わせてしまうと、
家を売却する人がいなくなり、中古物件が流通しなくなるからです。
従って、引渡し後に見つかった瑕疵は、売主が業者であれば責任を負いますが、
個人が売主の場合は責任を負わないとする特約も有効、となるのですね。
それではまた。