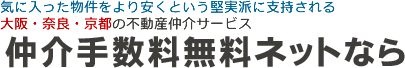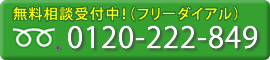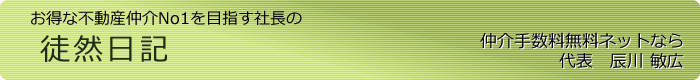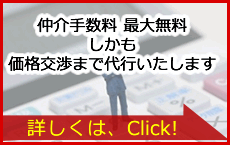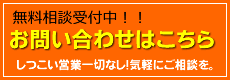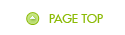こんにちは、辰川です。
住まいの快適さをはかる要素に、部屋の温度(室温)があります。
室温についていえば、部屋が外気を接する度合いが少ないほど快適になります。
これを一戸建てやマンションで考えてみると、
一戸建ては、必ず6方向(天井・床面と、東西南北の壁面)で外気と接しています。
これに対して、マンションは壁を隔てて、隣家と接しているだけなので、
一戸建てほど外気と面していません。
これが、比較的快適なマンションが多いといわれる理由の一つです。
ところが、同じマンションの中でも、住戸の位置によって室温に差があります。
これは、住戸が外気の影響を受けやすい位置にあるかどうかによります。
では、マンションの中で、もっとも快適な住戸はどこでしょうか。
それは、真ん中にある住戸です。
たとえば、一般的に最も外気の影響を受けやすいのが最上階の角部屋。
角部屋は眺望に優れているため、相場が少々高くても、常に人気の高い場所です。
しかし、日差しや風を遮るものがないので、外気にさらされやすく、
冷暖房の効率が悪い分、光熱費がかさんだりします。
その反対に、日照条件が良くないといわれる1階部分は、
夏は比較的涼しくて快適なのですが、冬は底冷えしやいです。
これと同じことは、1階部分が駐車スペースになった、2階の住戸にもいえます。
それに引き換え、最も外気の影響が少ないのが、真ん中の住戸。
なぜなら、真ん中の住戸は、左右両側と上下階が、ほかの住戸で挟まれているからです。
実際、真ん中の住戸は冬場に暖房が要らない、という話をよく聞きます。
そうはいっても、エアコン等の設備が発達している今、空調の管理さえしっかり行えば、
いつでもどこでも快適な室温が望めます。
ただ、光熱費にもかかわる要素だけに、
最上階の眺めのよさや、一階住戸の専用庭さえ望まないのであれば、
真ん中の住戸を選ぶのも、あながち間違いではありません。
それではまた。