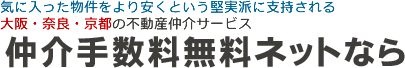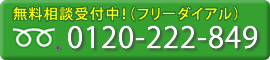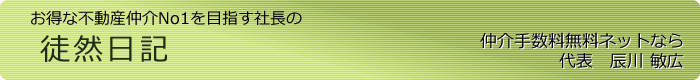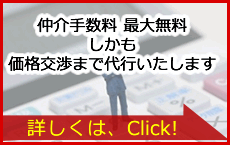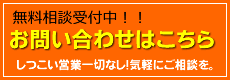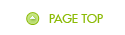こんにちは、辰川です。
住宅ローンの本審査が無事クリアしたからといって、これで金が借りられるというわけではありません。
つまり、審査承認の通知が下りただけでは、まだローンの融資が確定していないからです。
さらに、もう1つだけ最後の手続きが待っています。
それが、「ローン契約」ですね。
これを正式には「金銭消費貸借契約」といいますが、
いわば、お金を借り入れる正式契約のことです。
ローン契約は、残金決済を控えた数日前に行いますが、
この手続きのなかで、住宅ローンの借入内容をすべて取決めるのです。
例えば、融資額や返済期間、固定金利か変動金利の選択、融資実行日、口座からの引落日など。
このとき、まだ変動か固定かで迷っていたら、
窓口でシュミレーションを見せてもらって決めればよいでしょう。
ところで、ローン契約の際、必要なものとしては、
申込人の実印と印鑑証明書、家族の住民票があります。
また、過去に取引のない銀行であれば、銀行口座を新たに作りますから
銀行印も必要です。
なお、この時点で銀行の事務手数料や、保証会社への保証料の支払いは行いません。
さて、ローン契約の手続きには、仲介業者の同行はとくに必要ありません。
自分で銀行の窓口で行けば、せいぜい1時間程度で終わる手続きです。
たが、銀行の営業日は平日なので、気を付けたいものです。
但し、大阪や奈良、京都などの各金融機関の「住宅ローンセンター」では、
土日の手続きを行っていることもあるので、平日に時間の取れない人は要チェックといえますね。
さて、不動産購入の手続きも、次回がいよいよ最後となります。
次回は融資の実行について。
それではまた。