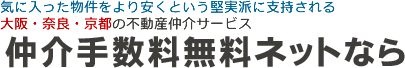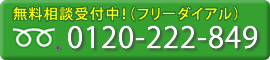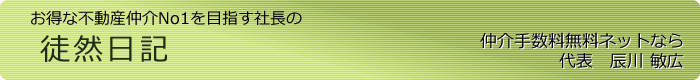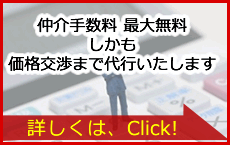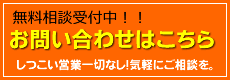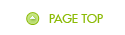こんにちは、辰川です。
今回は、マンションと一戸建ての違いを、
暑さと寒さ、管理面、近所付き合いの面から見ていきましょう。
何といっても両者には、建物の構造の違いがあります。
マンションの構造は、RC(鉄筋コンクリート造り)なので、当然がっしりしています。
一方、一戸建ては多くが木造です。がっしり感ではRCに劣りますが、
建物の軽さが、地震の際はメリットにつながります。
一戸建てでも大手住宅メーカーの場合は、鉄骨プレハブですが、
これも軽量鉄骨なので、堅牢さで云えば木造と大差ありません。
さて、RC造りの良さは、断熱と気密性の高さにあります。
それが冷暖房の効率性、省エネ性につながります。
とくに、購入する物件の上下階・左右隣りに住戸があれば、
真冬でもエアコンに頼らなくてもすみますし、
床暖房のなしでも快適に過ごせるはずです。
ただし、夏場の最上階は、昼間の熱を貯めこむので、
深夜まで冷房のお世話にならなければなりません。
冬場は、逆にRC構造の気密の高さが、結露を呼び込むので、
換気をこまめに行わないと、毎朝窓の水滴を拭く羽目になります。
これに対して、一戸建ては木造なので、建築時もメンテナンス時も
比較的低コストで済みます。
また、大阪や奈良は比較的温暖なので、高気密住宅でもないかぎり、
ひどい結露に見舞われることもありません。
維持管理については ご存知の通り、マンションは毎月、管理費がかかります。
でも、一戸建てはそうした費用は一切かかりませんね。
その代り、マンションは廊下や階段、ゴミ置き場等の清掃はすべてが、
管理会社任せ。住人は何もする必要はありません。
一戸建ては自宅・庭だけでなく、家の前の掃除、ゴミ置き場の清掃も
すべて自分たちが行います。
ただ、これも考えようによっては、庭木をいじったり、日曜大工など
器用にこなせる人は、間違いなく一戸建てが似合っています。
一方、庭の手入れや、面倒なことがちょっと苦手だったという人は、
やはりマンションが無難といえます。
ところで、マンションに住めば、玄関先さえ掃除することもありませんから、
隣同士であっても、まず顔を合わせる機会はないです。
そんな気遣いのない生活が楽!と思えば、やはりマンションが合っています。
一戸建てであれば、年に1?2回の溝そうじ、公園の草抜き、地域の行事に駆り出されます。
ゴミ当番も持ち回りですから、どうしても近所づきあいは必要になります。
いかがでしたか?
家の手入れ、ご近所付き合いがあまり苦にならない人は一戸建てがよいですね。
そうでない人が一戸建てに住むと、近所で浮いた存在になりかねません。
本当にちょっとしたことですが、気に留めておいてくださいね。
次回は、セキュリティ面について。
それではまた。