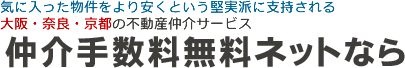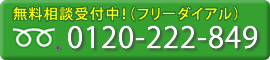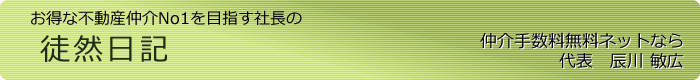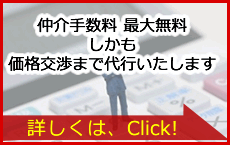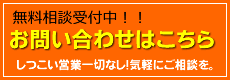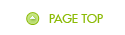不動産を購入するとき、つい物件価格のほうに目がいってしまいます。
でも、物件価格以外にかかってくるお金があります。
こんにちは、辰川です。
私たちが車を購うとき、車両代とは別に、ナンバー取得費や税金、保険がかかってくるのと同じように、
マンションや一戸建ての場合も、物件価格だけを用意しても自分のものとはなりません。
では、不動産を購入するにはどんな費用が掛かってくるのでしょうか。
今回は、不動産の「諸費用」についてです。
不動産の諸費用については、大きく分けて、税金と保険、ローン関連、報酬の4つがあります。
それぞれ見ていきましょう。
1.「税金」…売買契約書に貼る印紙、登記にかかわる登録免許税(所有権移転、抵当権)、決済時の固定資産税精算金、入居後の不動産取得税
2.「保険」…火災保険(10年分)や地震保険料(1年分)、フラット35の団体信用保険。
3.「ローン関連」…銀行への保証料や事務手数料
4.「手数料または報酬」…不動産業者への仲介手数料と、司法書士報酬。
マンションの場合はこれに加えて、管理費と修繕積立金の精算があります。
諸費用がいくらかかるかの目安として、物件購入価格の約5%位をみておきたいところ。
つまり、2千万円の物件であれば約100万円前後、3千万円の物件で約150万円前後です。
いざ契約となったときに、慌てることがないよう、諸費用は当初から資金計画に組み入れておくこと。
また、自己資金から捻出できない場合は、金融機関のほうでも物件本体の融資とは別に、
「諸費用ローン」を用意していたりもします。
自己資金が貯まるまで待っていたら、せっかく訪れた購入時期を逃すこともありますから、
マイホームの取得を何年も待てない場合は、諸費用ローンの利用を検討してもよいでしょう。
ただその場合でも、返済能力の範囲内であるとことは勿論のこととして、諸費用ローンが
物件本体の金利、返済期間と同じなのかは必ず確かめておきたいところです。
それではまた。