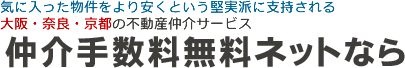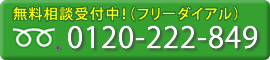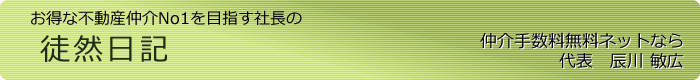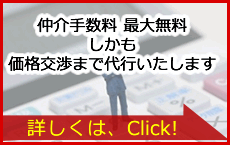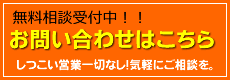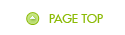こんにちは、辰川です。
不動産の決済も終え、マイホームの引渡しを受けると、
次はいよいよ新居への引っ越しです。
その引越しの際には、一つだけやっておかねばならないことがあります。
それが、新居のご近所への挨拶まわりですね。
近頃では挨拶をしない人も増えてきていますが、
挨拶をしないことによる不利益や悪い印象は避けたいところです。
これをきちんと行えるかどうかで、ご近所のあなたに対する印象も変わりますから、
やはり挨拶には行っておいた方が良いです。
そこで、今回は、引越しの挨拶の仕方について。
これさえ知っておけば、気後れして、挨拶に行けなかったということも起こりません。
まず、挨拶にまわる範囲は、一戸建てであれば「向こう三軒両隣」が基本。
あとは裏手で顔を合わせることのあるお宅ぐらいです。
マンションの場合は、両隣りと上・下階のお宅になります。
マンションの場合、小さな子供がいるのであれば、
「うるさくなると思いますがよろしくお願いします」と言っておけば、
トラブルを未然に防ぐことにもなります。
次に、引っ越しの挨拶は手ぶらというわけにはいきませんね。
といっても、高価な品は相手に気を使わせますから、
洗剤やタオル、ラップなど日用品が無難ですね。
ところで、挨拶に行くタイミングですが、引越し後1週間以内に
済ませるのがよいです。
ベストなのは、引っ越し当日か、その翌日。
数回訪ねても不在のお宅は、手紙をポストか郵便受けに入れておきましょう。
その際、挨拶品は、手紙と一緒に袋に入れてドアノブにかけておけばよいです。
いかがでしたか?
引越し時の挨拶で、相手の印象を決めつけてしまう人はたくさんいます。
「いつまで経っても挨拶に来ない…」と思われないよう、
挨拶はさっさと済ませておくことですよ。
それではまた。