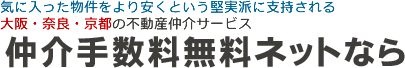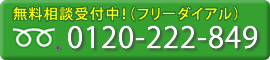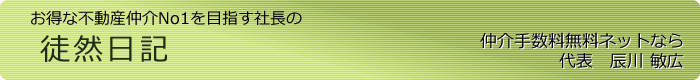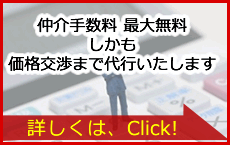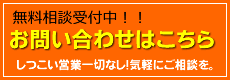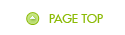こんにちは、辰川です。
住宅ローンの金利には、大きく分けて2つのタイプがあります。
すなわち、「変動金利型」と「固定金利型」です。
さて、住宅ローンを組むときに誰もが悩むのが、
変動か固定かという選択ではないでしょうか?
そこで、今回は変動と固定、それぞれのメリット、デメリットについてです。
まず、変動型金利とは、半年に一度、金融情勢の変化に応じて
金利が見直されるタイプ。
この変動型のメリットは、概して固定金利型よりも金利が低水準にあることです。
しかも銀行によっては、優遇キャンペーンでさらに低金利が期待大。
逆に変動型のデメリットは、借入れの段階では総返済額を計算できないことです。
それだけに、将来金利が上がった時の備えも必要かもしれませんね。
一方の 固定型金利は、借入時の金利がそのまま最後まで変わりません。
ですから、固定型のメリットとは、借入れ段階で、総返済額がわかること。
将来にわたり金利が見直しされませんから、安定した返済が可能といえるでしょう。
逆に固定型のデメリットは、変動型に比べ、概して金利が高いことです。
ということは、高金利時に借りると、最後までずっと高金利のままで推移することに・・
では、変動金利、固定金利、どっちの住宅ローンが得なのか?
実は、お金の貸し手側である銀行は、全期間固定金利の住宅ローンの貸出を嫌がります。
なぜなら、固定金利は貸し手側が金利変動リスクを負っているからです。
逆に言えば、変動金利の住宅ローンは借り手側が金利の変動リスクを負っているといえます。
従って、変動金利で貸したほうが銀行にとっては有利になります。
さて、借りる側にとって、変動と固定のどちらが得かという疑問ですが、
実際にはローンを完済してからでないと分からない、というのが正直なところです。
あなたが住宅ローンを返済し終えたとき、金利が上がっていなかったら、変動金利を選んで正解だったでしょうし、
その反対に、当初より金利が上がっていれば、固定金利を選んだことが正解となるのです。
いかがでしたか?
変動と固定、それぞれのメリット、デメリットをよく検討し、
ぜひあなたに一番有利な住宅ローンを選択してくださいね。
次回は住宅ローンの減税について。
それではまた。