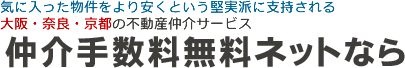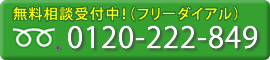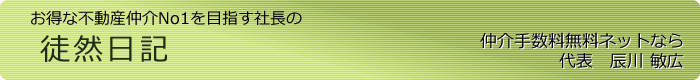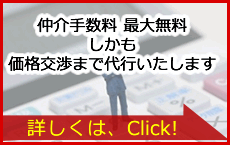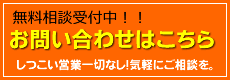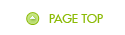こんにちは、辰川です。
ネット銀行を利用して住宅ローンを組みたいという人が増えています。
その魅力は、低い金利にあります。
では、単純に低金利というだけで飛びついてしまってよいものか?
まず、ネット銀行のデメリットも理解したうえで、自分に合っているかどうか判断すべきです。
ところで、ネット銀行の住宅ローン金利が低さには、当然ながら理由があります。
それは、実店舗を持たないために、コストを圧縮できること。
そのため、ネット銀行には次のようなデメリットもあります。
1.審査時間が長い
基本は郵送による書類のやりとりとなるので、実店舗のある銀行に比べて、
日数を要します。
2.実店舗が近くにない
銀行の担当者と対面してのやりとりができないので、書類にミスがあっても
その場で確認することができません。
3.初期費用が高い
ネット銀行の多くは、保証会社を利用しないので、保証料はかかりませんが、
その一方で事務手数料が借入額の2%程度かかります。
4.自分で手続きをしないといけない
ネット銀行を利用する場合、不動産仲介会社に頼らずに、自分で手続きを行わないとなりません。
住宅ローンの手続きは煩雑で面倒だと感じる人は、避けた方が無難です。
そのほか、ネット銀行が保証料無料であるのにも、理由があります。
というのは、ネット銀行は保証会社を使っていないからです。
一般的な住宅ローンでは保証会社を使いますが、万が一、利用者に支払いの遅延した場合に
金融機関は保証会社に支払いを請求します。
しかし、ネット銀行では保証会社を使わないため自社の対応となります。
そのため、未払い分の回収を自社で行えばコスト増加につながるため、ローンの審査を厳しくなっています。
これに対して、実店舗のある銀行ではどうでしょうか。
•店舗に出向いて、顔を合わせて話せる
•何かあったとき、親身になって相談にのってくれる
•個別の対応にも多少の融通がきく
このように、多少金利は高いですが、利用者にとって、数字に表れないメリットがあるのです。
いかがでしたか?
ローンは借りる際の条件だけを重視しがちですが、後々のことも考えておきたいもの。
あなたがネット銀行を検討しているならば、ぜひ参考にしてくださいね。
それではまた。