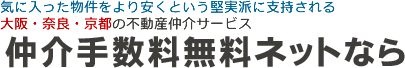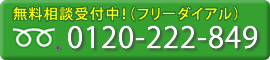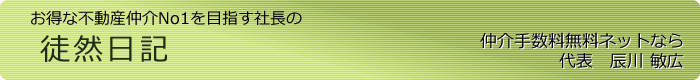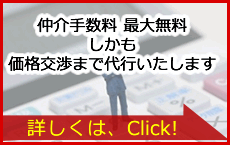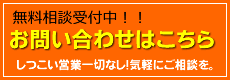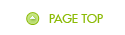こんにちは、辰川です。
若い頃は家なんて、興味ないと思っていても、結婚や子供の成長がきっかけで、
持ち家を意識する人は多いですよね。
その一方、終身雇用制度も崩れたことで、住宅ローンで大きな借金をつくるよりも
一生を賃貸暮らしでも良いと考える人もいます。
では、賃貸と持ち家では一体どちらが得なのでしょうか。
そこで今回は、持ち家と賃貸の支出面についてお話しします。
賃貸で良い条件の部屋を借りようとすると、敷金や礼金が必要だったりします。
例えば、敷金だけで数十万円は掛かることも・・
賃貸に住むと、自分の不注意でなければ、家主の負担で修理されますが、
汚れや破損があれば、敷金からハウスクリーニング代や修理費を引かれます。
では、持ち家の場合はどうなのか。
今では金融機関で100%ローンを組めるようになりました。
でも、仲介手数料や登記費用、銀行の手数料、火災保険といった諸費用も馬鹿になりませんから、
ある程度の頭金を準備したいところです。
それに、持ち家を手に入れたあとも、毎年、固定資産税がかかります。
しかも一戸建ては、建物や設備に不具合がでれば、自分で直さなくてはなりません。
これがマンションになると、自分が直さなくてもよいかわりに、管理費や修繕積立費が毎月かかります。
以上のことから、持ち家を手に入れる場合の支出をみると、
賃貸が圧倒的に安上がりなのがわかりますね。
ところが、そんな賃貸も長く住めば住むほど、得とはいえなくなってきます。
なぜなら、持ち家を手に入れた人は、将来住宅ローンさえ完済したら、
特に大きな支払いはなくなってしまうからです。
その後は、毎年、固定資産税を納付するだけで済みます。
マンションの場合であっても、固定資産税以外に、管理費や修繕費が加わるだけ。
一方、賃貸に暮らす人は、家賃の支払いだけは延々と続きます。
この辺りから、持ち家の人との逆転が始まります。
ある調査によれば、持ち家を住宅ローン35年間で完済した場合と、同額の家を50年間
借りた場合とでは、持ち家のほうは賃貸よりも2千万円ほど安く済むといいます。
単に支出額だけで、持ち家と賃貸を比較することはどうかと思いますが、
ローン完済後の気持ちのゆとりは、賃貸を借りる場合には得られないのは確かなようです。
それではまた。