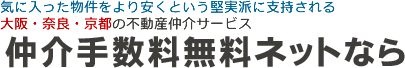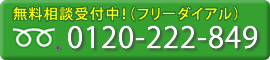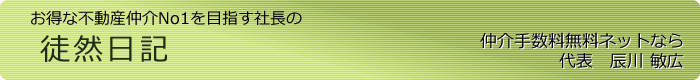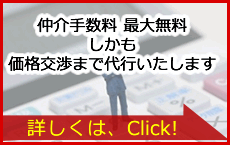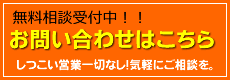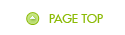こんにちは、辰川です。
新婚での家探しは、住むエリアも大切ですが、
まずは賃貸と購入のどちらにするかという問題があります。
そこで今回は、新婚夫婦の住まいとしての賃貸と購入について。
新婚夫婦の場合、賃貸でも分譲でも、
すぐに子どもを考えている場合、
子どもと暮らせる物件かどうかは大事です。
次に、新婚夫婦にとっての賃貸と持ち家にはそれぞれ
どんなメリットデメリットがあるかです。
賃貸にするメリット・デメリット
・賃貸に選ぶと、転職や子どもの誕生など生活の変化があった時、
手軽に住み替えやすいことがメリットですよね。
・設備が壊れたときも、経年変化が原因なら、
オーナー負担で直せてもらえたりします。
・壁に穴を開けたり、部屋を勝手に
アレンジするのはご法度。
・デメリットとしては、生涯にわたり
賃貸住宅に住み続けた場合には、
老後も住居費用の負担が大きくなります。
持ち家にするメリット・デメリット
・若いうちにマイホームを購入すると、
住宅ローンの借入期間が長期にできるので
返済しやすくなります。
・購入時に頭金や仲介手数料など諸費用はかかりますが、
老後の住居費の負担がないので、
「マイホーム=資産」ととらえたら納得できます。
・我が家としての愛着が湧きますから、
暮らしにも落ち着きがでてきます。
・一戸建ての場合、建物のメンテナンス費用は
すべて自己負担になります。
・マンションの場合は、
外壁など共用部分は修繕積立金で対応できますが、
居住スペースである専有部分にかかる修繕費は、
別に用意しておかねばなりません。
さて、新婚当初はお互いの生活スタイルが知らなかったり、
子どもの人数や将来の仕事といった不確定要素もありますね。
そういう意味では、先でマイホームを視野に入れつつ、
新婚当初は賃貸で暮らしてみて、頭金が用意できたら、
生活に合った住宅を購入するのもよいかもしれません。
それではまた。